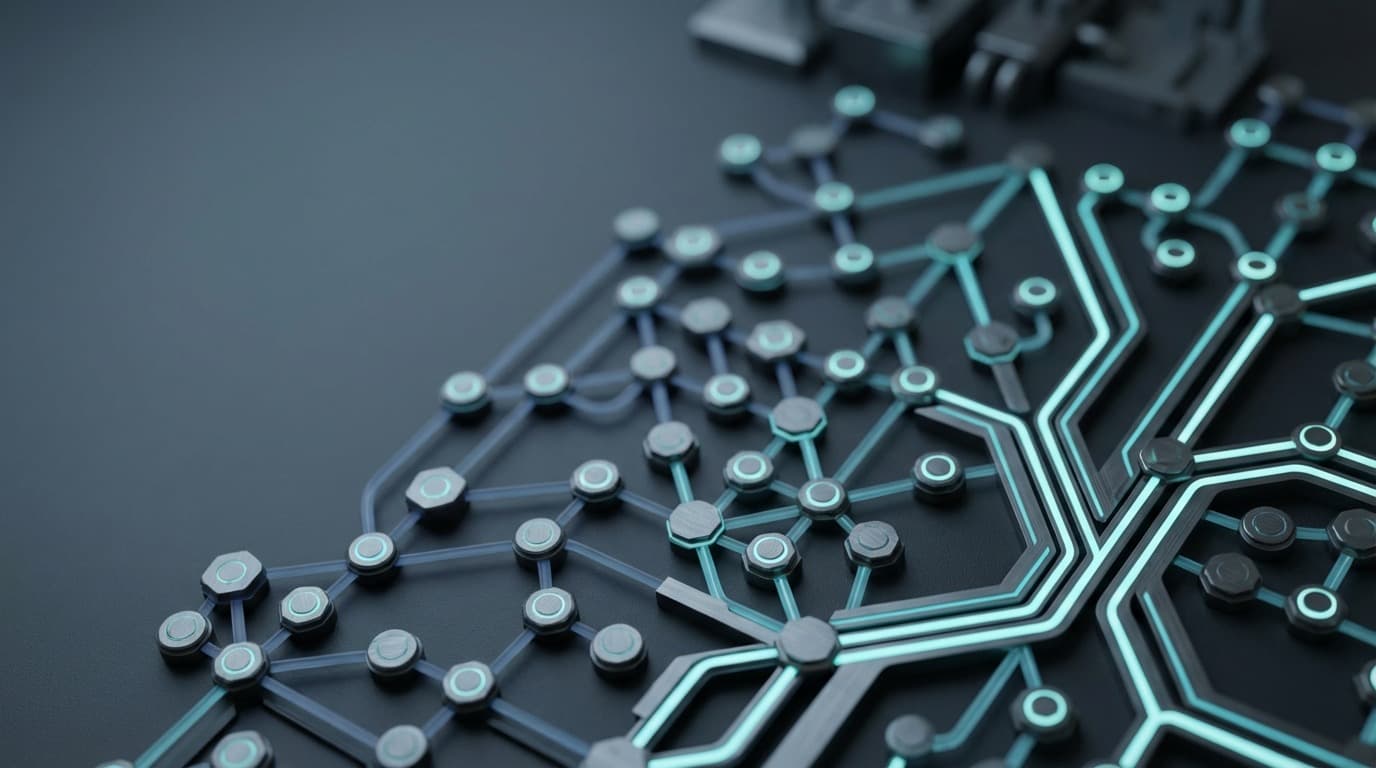生成AIの急速な普及により、AIサービスの国際取引が爆発的に拡大している。日本のデジタルサービス貿易赤字は2025年上半期だけで240億ドルに達し、その多くが米国テック企業へのAI関連支出である。本稿では、AIに関税が課される可能性を国際課税制度の観点から検証し、2035年以降の長期シナリオと日本が取るべき政策オプションを提示する。
なぜ今「AI関税」を論じるのか
従来の関税制度は、物理的な財の国境通過を前提として設計されてきた。しかし、AIサービスは国境を意識することなく、API呼び出しという形で瞬時に提供される。OpenAIのGPT-4、AnthropicのClaude、GoogleのGeminiといった大規模言語モデル(LLM)へのアクセスは、エンドユーザーの所在地とは無関係に、米国のデータセンターから提供される。
この「価値の無形化」は、国際課税制度に根本的な問いを突きつけている。製造業時代の課税ルールは、工場の所在地や製品の物理的な移動に基づいていた。しかしAI時代には、価値創造の大部分がモデルの学習(トレーニング)段階で行われ、推論(インファレンス)はどの国のサーバーでも実行可能である。
OECDは2021年以降、「BEPS 2.0」として知られる国際課税改革を推進してきた。第1の柱(Pillar One)は、大規模多国籍企業の利益を市場国に再配分する仕組みであり、第2の柱(Pillar Two)は15%のグローバル最低法人税率を設定するものである。しかし、2025年1月にトランプ政権が発足すると、米国はOECD合意からの事実上の離脱を宣言し、Pillar Oneの実現は「当面待たなければならない」状況となった(OECDコーウィン税務センター長、2025年5月)。
この空白を埋めるように、各国は独自のデジタルサービス税(DST)を導入または再検討している。フランス、イタリア、スペイン、英国などは既にDSTを施行しており、EUは2026年までに年間375億ユーロの税収を見込んでいる。これに対し、トランプ政権は2025年2月、DST導入国に対する報復関税の検討を指示した。
国際動向の分析:三極構造と新興国の台頭
米国:AI覇権と輸出規制の揺らぎ
米国のAI政策は、2025年を通じて大きく揺れ動いた。バイデン政権末期の2025年1月15日、商務省産業安全保障局(BIS)は「AI拡散規則」を発表し、先端AI半導体の輸出を三層構造で管理する方針を示した。しかしトランプ政権発足後、政策は一貫性を欠いた。
2025年3月には42の中国企業がエンティティリストに追加され、4月にはNVIDIA H20チップの中国向け輸出にライセンスが必要となった。ところが同年12月、トランプ大統領は方針を転換し、米国半導体メーカーが中国に高性能AIチップを販売することを許可した。その条件は、売上の25%を米国政府に納めることであった。
この「25%ステーク」方式は、事実上のAI関税と見なすことができる。物理的な財ではなく、AIチップという戦略物資の取引に対して、国家が収益の一部を徴収する仕組みである。2026年1月14日、ホワイトハウスは半導体に25%の関税を即時発動すると発表し、これを中国向けH200輸出許可と連動させた。
中国:国内AI産業の強化と代替戦略
中国は米国の輸出規制に対し、国内AI半導体産業の育成で対抗している。ファーウェイは2025年に20万個、2026年には30万個のAIチップ(910C)を生産すると予測されている。米国が100万個のH200輸出を許可した場合、中国に設置されるAIコンピュート能力は国産チップのみに依存する場合と比較して250%増加する計算となる。
同時に中国は、グローバルサウスへのAI輸出促進を加速させている。アリババのQwen3モデルは119の言語・方言に対応し、ベンガル語、ビルマ語、ウルドゥー語など、西側のAIモデルがカバーしていない言語も含まれる。これは単なる技術競争ではなく、AI標準と影響力をめぐる地政学的競争である。
EU:規制主導のデジタル主権
EUはAI規制において最も包括的なアプローチを取っている。2024年8月に発効したEU AI法は、GDPRと同様の域外適用を持ち、EU市場にAIシステムを提供するすべての事業者に適用される。禁止されるAI慣行は2025年2月から、汎用AI(GPAI)ルールは2025年8月から、その他の規定は2026年8月から施行される。
違反に対する制裁金は最大3,500万ユーロまたは全世界売上高の7%であり、これは事実上の「AI規制関税」として機能する。EU域内でビジネスを行う米国AI企業は、コンプライアンスコストを価格に転嫁せざるを得ず、結果としてEU消費者が間接的にその負担を負う構造となっている。
グローバルサウス:BRICS宣言とデジタル主権の要求
2025年のBRICS AI ガバナンス宣言は、ブラジル議長国の下で11カ国(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ、サウジアラビア、エジプト、UAE、エチオピア、インドネシア、イラン)が署名した。宣言は、国連主導の枠組み、デジタル主権、包括的なグローバルガバナンスを強調し、各国がAI研究能力の開発、技術革新の促進、データ保護について自律的に規制枠組みを構築する権利を確認した。
新興国の主張の核心は「技術移転」と「公平なアクセス」である。現状では、AIの恩恵は先進国に集中し、グローバルサウスはAIを「輸入する側」に留まっている。この不均衡を是正するための手段として、将来的にはAIサービスへの課税や技術移転要件が検討される可能性がある。
AI関税の技術的・制度的実現可能性
課税対象の定義問題
「AI関税」を設計する上での最大の障壁は、課税対象の定義である。以下のいずれを課税対象とするかによって、制度設計は大きく異なる。
- AIモデル自体:モデルのパラメータ数や学習コストに基づく課税。しかしオープンソースモデルの扱いが困難。
- API呼び出し:推論リクエスト単位での課税。技術的には実装可能だが、VPN経由のアクセスなど回避が容易。
- コンピュート資源:GPU/TPUの稼働時間や消費電力に基づく課税。データセンターの所在地に依存。
- 生成トークン:AIが出力したテキスト・画像・音声のトークン数に基づく課税。測定は可能だが、価値との相関が不明確。
現時点で最も実現可能性が高いのは、既存のデジタルサービス税の枠組みを拡張する方法である。すなわち、一定規模以上のAIサービス事業者に対し、市場国での売上高に基づく課税を行う方式である。
移転価格と恒久的施設の課題
OECDは2024年2月、移転価格ガイドラインに「Amount B」を追加し、2025年1月以降の会計年度から適用を開始した。しかしAmount Bは有形財の流通活動を対象としており、AIサービスは適用範囲外である。
また、2025年11月に更新されたOECDモデル租税条約では、リモートワークによる恒久的施設(PE)の認定基準が明確化された。従業員の遠隔勤務が総労働時間の50%未満であればPEは発生しないが、50%以上の場合はPE認定の可能性がある。AIサービスの場合、「従業員」がどこにも常駐せず、サーバーのみが稼働する状況では、従来のPE概念の適用が困難である。
執行の実務的課題
仮にAI関税が制度化されたとしても、執行には多くの課題がある。AIサービスはインターネット経由で提供されるため、物理的な税関検査は不可能である。課税当局がAPI呼び出しをリアルタイムで監視することは、プライバシーとセキュリティの観点から受け入れがたい。
現実的なアプローチは、一定規模以上のAIプロバイダーに対する報告義務と、金融機関を通じた徴収メカニズムの構築である。これはVAT/消費税の国際的な執行と類似したモデルとなる。
長期シナリオ分析:2035年の世界
シナリオA:グローバル協調(確率25%)
最も楽観的なシナリオでは、米国、中国、EUが国際AI課税ルールで合意に至る。OECDまたは国連の枠組みの下で、AI企業の利益を市場国に配分する仕組みが構築され、DSTや報復関税の応酬は収束する。
このシナリオの前提条件は、米中関係の改善と、AIガバナンスに関する国際的なコンセンサスの形成である。現状では実現可能性は低いが、気候変動対策のような「共通の脅威」への対応として、AI規制の国際協調が進む可能性はゼロではない。
シナリオB:ブロック化(確率50%)
最も蓋然性の高いシナリオは、米国主導ブロック、中国主導ブロック、EU独自圏の三極分裂である。各ブロックは独自のAI標準、課税ルール、データ流通規制を持ち、ブロック間のAIサービス取引には高い障壁が存在する。
このシナリオでは、日本は米国ブロックに属しつつも、EUとの規制互換性を維持するという「二重適合」戦略を取ることになる。コンプライアンスコストは上昇するが、両市場へのアクセスは維持される。中国市場からは事実上排除されるか、大幅に制限される。
シナリオC:規制競争(確率25%)
最も悲観的なシナリオでは、国際協調が完全に失敗し、各国が自国AI産業の保護と誘致を競う「底辺への競争」が発生する。AIデータセンターの誘致を目指す国々は、税制優遇や規制緩和を競い合い、「AI租税回避地」が出現する。
一方で、AI覇権国である米国と中国は、自国企業を保護するための一方的措置を乱発し、世界のAIエコシステムは分断される。中小国や新興国は、いずれかの陣営への依存を深めるか、独自のAI能力構築を試みるかの選択を迫られる。
日本への影響と政策オプション
現状認識:深刻化するデジタル赤字
日本のデジタルサービス貿易赤字は2025年上半期に240億ドルに達した。この赤字の大部分は、クラウドサービス(AWS、Azure、Google Cloud)とAIサービス(OpenAI、Anthropic等)への支払いである。日本企業のDX推進がそのまま米国テック企業への資金流出となっている構図である。
日本は米国のDST報復対象国には含まれていない。これは日本がデジタルサービス税ではなく、内外無差別の消費税(10%)を適用しているためである。しかし、この「中立的」姿勢が日本のAI産業育成にとって最適かどうかは検討の余地がある。
政策オプション1:現状維持(消極的適応)
米国との同盟関係を最優先し、AI課税については国際的な合意形成を待つアプローチである。日本はOECD議論に参加しつつ、独自のDSTは導入しない。2025年5月に成立したAI推進法の「イノベーション優先」路線を維持する。
メリット:米国との摩擦回避、外資AI企業の日本市場参入促進
リスク:デジタル赤字の継続的拡大、国内AI産業の競争力低下
政策オプション2:戦略的AI産業育成
政府が2024年11月に発表した「AI・半導体産業強化枠組み」(2030年までに10兆円の公的支援)を加速させ、国内AIエコシステムの構築を優先するアプローチである。R&D税額控除(AI関連は40%)を最大限活用し、国産LLMの開発を支援する。
メリット:長期的な技術自立、AI関連雇用の創出
リスク:短期的な財政負担、グローバルAI企業との技術格差
政策オプション3:EU型規制の導入
EU AI法と互換性のある規制枠組みを導入し、高リスクAIシステムへの適合性評価や透明性要件を義務化するアプローチである。これにより、日本企業のEU市場アクセスを円滑化しつつ、外資AI企業にも同等のコンプライアンス負担を求める。
メリット:EU市場との相互運用性、AIリスクへの対応強化
リスク:イノベーション阻害の可能性、米国との規制競合
政策オプション4:「AI消費税」の検討
既存の消費税の枠組みを活用し、国外から提供されるAIサービスへの課税を強化するアプローチである。2015年に導入された電子サービスへの消費税適用を拡大し、AIサービス提供者への登録義務と納税義務を明確化する。
メリット:WTO整合的(内外無差別)、追加的な税収確保
リスク:AI利用コストの上昇、中小企業への負担
政策提言
以上の分析を踏まえ、日本政府に対し以下の政策を提言する。
第一に、AI関連の国際課税ルール形成に積極的に関与すべきである。OECD Pillar Oneの交渉が停滞する中、日本は米国と新興国の間の「橋渡し役」として、実現可能な妥協案の策定に貢献できる立場にある。G7およびG20の場を活用し、AI課税の原則(例:市場国への利益配分、二重課税の防止)について国際的なコンセンサス形成を主導すべきである。
第二に、「AI消費税」の制度設計を開始すべきである。これはDSTとは異なり、内外無差別の消費課税であるため、WTO整合性を維持できる。具体的には、一定規模以上の国外AIサービス提供者に対する登録義務、リバースチャージ方式の適用範囲拡大、デジタルプラットフォームを通じた徴収メカニズムの構築を検討すべきである。
第三に、デジタル赤字の構造的要因に対処すべきである。国産クラウド・AIインフラへの投資促進、AI人材の育成・確保、スタートアップ支援を通じて、日本がAI消費国から生産国への転換を図るべきである。2030年までに10兆円の公的支援を着実に執行し、民間投資を誘発する環境を整備すべきである。
第四に、ブロック化シナリオへの備えを進めるべきである。米国との同盟を基軸としつつ、EUとのデジタル貿易協定の深化、ASEAN・インドとのAI協力枠組みの構築を並行して進めるべきである。特定のAIエコシステムへの過度な依存は、地政学的リスクを高める。
結論
「AIに関税は課されるのか」という問いに対する答えは、「形を変えて既に課されつつあり、今後さらに拡大する」である。
米国の半導体輸出規制と25%関税、EUのAI法による域外適用、各国のDST、そして新興国のデジタル主権要求——これらはすべて、AI時代の「関税」の萌芽形態と見なすことができる。物理的な財に課される伝統的な関税とは異なり、これらは規制コスト、コンプライアンス負担、市場アクセス制限という形で機能する。
2035年に向けて、世界のAIエコシステムがグローバル協調、ブロック化、規制競争のいずれの方向に進むかは、今後10年の政策選択にかかっている。日本は、米国との同盟を基軸としつつも、多様なシナリオに対応できる柔軟性を維持すべきである。AI関税の時代に備え、国際ルール形成への関与、国内AI産業の育成、そして税制の適応を同時に進めることが求められる。
FAQ
AIサービスに関税を課すことは技術的に可能か?
従来の物理的関税と同じ形式は困難だが、デジタルサービス税(DST)や消費税の枠組みを活用した課税は技術的に可能である。一定規模以上のAIプロバイダーへの登録義務と、金融機関を通じた徴収メカニズムが現実的なアプローチとなる。
日本はデジタルサービス税を導入しているのか?
日本は特定のデジタル企業を狙い撃ちにしたDSTは導入しておらず、内外無差別の消費税(10%)を適用している。このため、米国の報復関税対象国には含まれていない。2015年から国外電子サービスにも消費税が適用されている。
OECD Pillar Oneの現状はどうなっているか?
2025年1月のトランプ政権発足後、米国はOECD国際課税合意への支持を事実上撤回した。OECDコーウィン税務センター長は2025年5月、Pillar Oneの議論は「待たなければならない」と述べており、実現の見通しは不透明である。
日本のデジタルサービス貿易赤字はどの程度か?
2025年上半期の日本のデジタルサービス貿易赤字は240億ドルに達した。その多くはクラウドサービスとAIサービスへの支払いであり、日本企業のDX推進が米国テック企業への資金流出となっている構造である。
EU AI法は日本企業にも適用されるのか?
EU AI法はGDPRと同様の域外適用を持ち、EU市場にAIシステムを提供する日本企業にも適用される。高リスクAIシステムを提供する場合、適合性評価や透明性要件への対応が必要となる。主要な規定は2026年8月から施行される。
参考文献
- AI and Digital taxation in 2025: Implementing the new global tax deal — Digital Watch Observatory
- The OECD/G20 Pillar 1 and Digital Services Taxes: A Comparison — Congressional Research Service, 2025
- U.S. Export Controls and China: Advanced Semiconductors — Congressional Research Service, 2025
- The New AI Chip Export Policy to China: Strategically Incoherent and Unenforceable — Council on Foreign Relations, 2025
- Understanding Japans AI Promotion Act: An Innovation-First Blueprint for AI Regulation — Future of Privacy Forum, 2025
- Gains from Digital Services Imports in Japan — Center for Strategic and International Studies
- BRICS AI Governance Declaration 2025 — Nemko Digital
- The future of tax policy: A public finance framework for the age of AI — Brookings Institution
- The 2025 Update to the OECD Model Tax Convention — OECD, November 2025