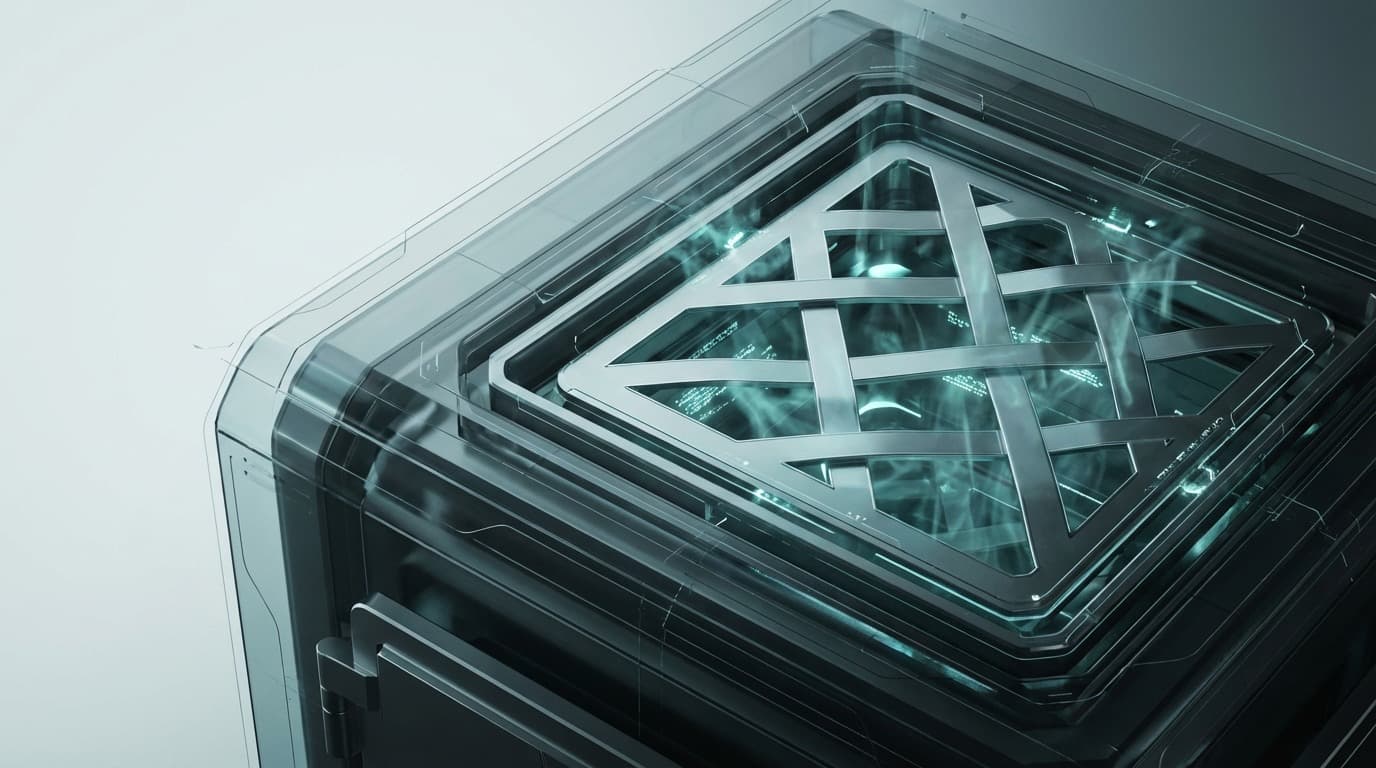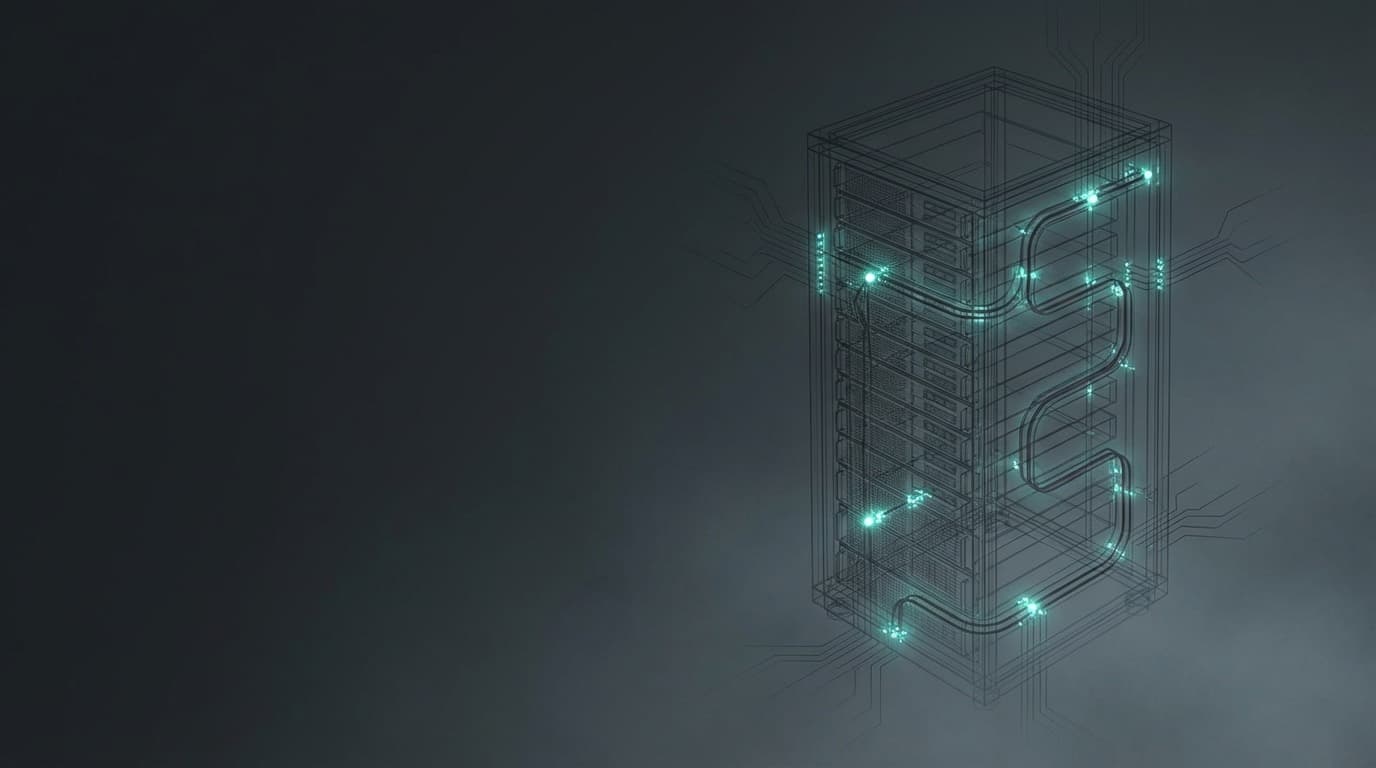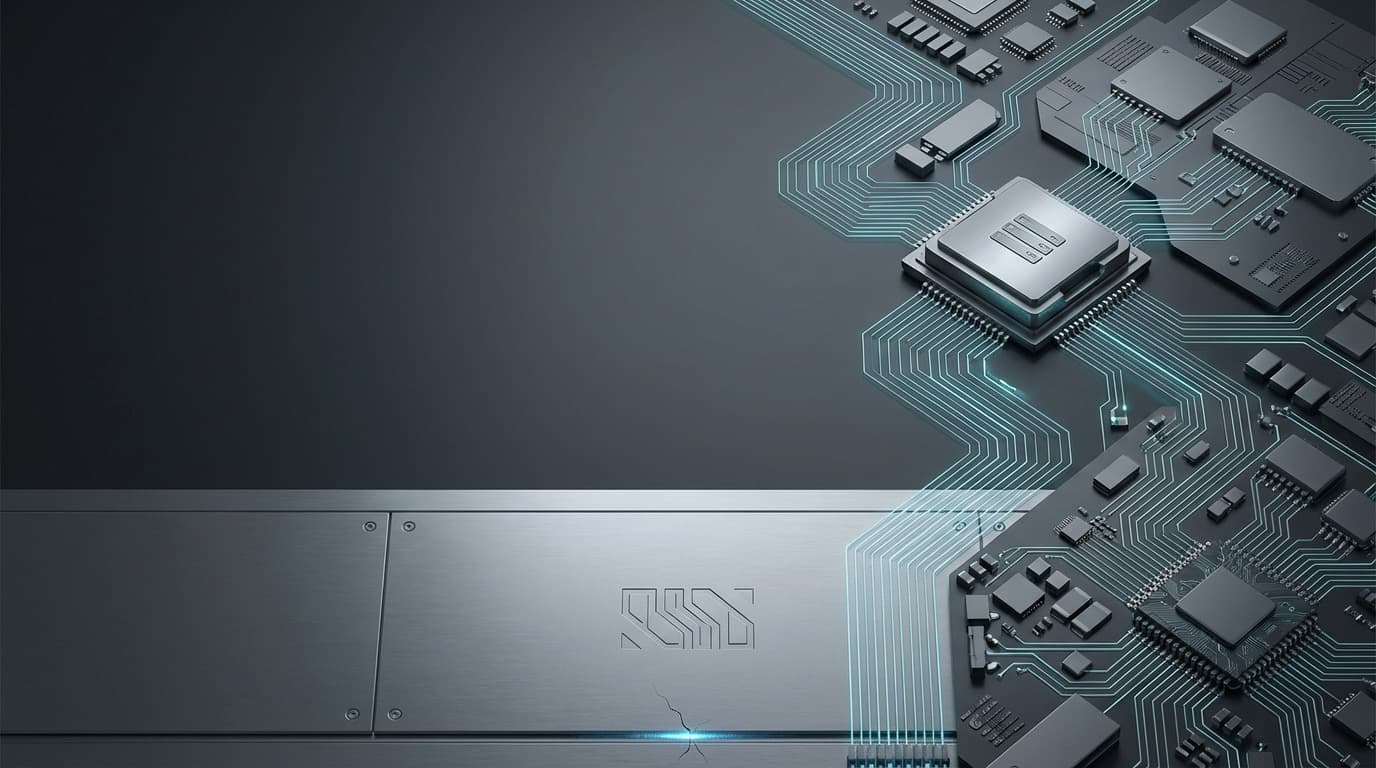SolarWinds Web Help Desk(WHD)を巡っては、Javaのデシリアライゼーション(untrusted deserialization)に起因するリモートコード実行(RCE)が実際に悪用され、CISAのKnown Exploited Vulnerabilities(KEV)カタログに登録されている。とりわけCVE-2025-40551は、ネットワーク経由・未認証でのコード実行に到達し得るクラスの欠陥として扱われ、WHDをインターネット公開したまま運用している組織にとって即応が必要な部類である。
本稿では、(1) KEV登録とCVE-2025-40551の技術的な位置付け、(2) Javaデシリアライゼーション脆弱性が再発し続けるメカニズム、(3) 現場で観測された wrapper.exe→java.exe→cmd.exe のプロセス連鎖、(4) Catbox経由のManageEngine RMM配備からVelociraptor/Cloudflaredに至るポストエクスプロイトの各段階を、一次情報に基づき整理する。
KEV登録とCVE-2025-40551の位置付け(CVSS 9.8)
CVE-2025-40551は、SolarWinds Web Help Deskが「信頼できないデータのデシリアライゼーション」によりRCEへ至り得る脆弱性として扱われている。NVD(NIST)ではCVSS v3.1のベーススコアが9.8(Critical)であり、攻撃条件はネットワーク経由・低複雑度・権限不要・ユーザー操作不要である。
また、CISAのKEVカタログではCVE-2025-40551が「Known Exploited(既知の悪用)」として登録されている。KEVは“理論上危険”ではなく、実際の悪用が確認された脆弱性を優先度付けするための枠組みであり、登録日()と対処期限()が明示される点に特徴がある。
ベンダ側の信頼できる更新情報(修正バージョン、既知の侵害指標、暫定的な運用上の回避策)と、KEVのような運用優先度のシグナルを突き合わせ、WHDを“境界内の業務ツール”として曖昧に扱わないことが重要である。
JavaデシリアライゼーションRCEの典型パターンと「再発」の理由
Javaのシリアライズ/デシリアライズは、ObjectInputStream 等を介してオブジェクトグラフを復元する。問題は、入力データが攻撃者により制御可能であり、かつ復元対象のクラス群(クラスパス上のライブラリ)に「ガジェット(gadget)」となるコードパスが存在する場合、復元処理そのものが任意コード実行へ転化し得る点にある。いわゆる“ガジェットチェーン”は、単体の危険APIではなく複数クラスの副作用が連鎖して成立するため、レビューや単純なパターン検知で取り切れない。
この種の欠陥が再発しやすい背景には、次の構造的要因がある。
- 業務アプリケーション内でJavaシリアライズが残存しやすく、機能的には「動いてしまう」ため置換が後回しになりやすい。
- 依存ライブラリの更新でガジェット条件が変動し、過去に「安全」と判断された経路が再び危険化し得る。
- 外部入力の境界(HTTPパラメータ、フォーム、API、アップロード、内部RPC)が複雑で、どの入力がデシリアライズへ到達するかが把握しづらい。
防御側の基本方針は、(a) 可能ならJavaシリアライズを廃止する、(b) やむを得ず残る場合はデシリアライズ対象のクラスを厳格に制限する(例: allowlistやObjectInputFilter)、(c) 攻撃面(管理系UI/API)の公開を最小化する、の組み合わせである。加えて、WHDのように運用上“停止しづらい”業務系コンポーネントほど、脆弱性がRCE級である場合はパッチ適用と同等にネットワーク分離を優先する判断が現実的である。
攻撃チェーン(初期侵入): wrapper.exe→java.exe→cmd.exe
現場で観測されるWHD侵害では、サービスプロセスのツリーがそのまま攻撃者の実行基盤になる。Huntressの報告では、WHDのプロセスとして wrapper.exe が java.exe を起動し、そこから cmd.exe が生成される流れが確認されている。WHDの“Javaアプリケーションとしての実体”が、エクスプロイト成立後にOSコマンド実行へ接続される典型例である。
この段階で重要なのは、侵害の根が「ツール導入」ではなく「アプリケーション層のRCE」である点である。RMMやトンネルは後続ステージであり、初期侵入の封じ込めは、(1) 脆弱なWHDの停止/隔離、(2) パッチ適用、(3) 侵害ホストのクリーン再構築(必要なら)を中心に据える必要がある。
ポストエクスプロイト(運用フェーズ): Catbox→ManageEngine RMM→Velociraptor→Cloudflared
攻撃者は、侵入直後に“手動運用の足”を確保し、その後に横展開と永続化を進める傾向がある。Huntressは、ファイルホスティング(Catbox)を経由してZoho ManageEngineのRMMエージェントをステージングし、正規ツールを悪用して継続的な遠隔操作を確立したと報告している。
RMMによる足場が確立された後、同報告ではActive Directory(AD)探索として、ドメイン参加端末の列挙(例: net group "domain computers" /do)が実行されたことが示されている。ここで得られる“横展開候補”は、以後の資格情報アクセスや管理共有の探索など、次のステージに直結する。
さらに同一系列の侵害で、Velociraptor(例: 0.73.4)が導入され、Cloudflare Workersドメインを利用したC2(設定ファイルclient.config.yamlの書き換えとサービス再起動を伴うフェイルオーバー)など、EDR/DFIR用途の正規ツールを転用した高度な運用が観測されている。防御側にとって厄介なのは、これらが“企業ネットワークに存在し得る正規バイナリ”であることで、単純なブラックリスト型の検知だけでは取り逃しやすい。
トンネリングについては、WHDホスト上でCloudflaredがインストールされ得ることが指摘されており、外向き通信の見直し(許可先の絞り込み、プロキシ経由強制、Egressフィルタ)と、サービス常駐・MSIサイレント導入・エンコードされたPowerShellの監視を組み合わせる必要がある。
検知・封じ込めの要点(プロセスツリーと“正規ツール悪用”の観点)
運用上の優先度は「パッチ適用」だけでは足りない。KEV登録済みである以上、すでに侵害済みである可能性も前提に置く必要がある。実務上のチェックポイントは次の通りである。
- プロセスツリー:
wrapper.exe/java.exeを祖先に持つcmd.exe、powershell.exe、msiexec.exeの生成。 - サイレント導入: MSIの無人インストール、特に外部ホスティング(Catbox等)からの取得痕跡。
- “正規だが不自然”な常駐: RMM(ManageEngine等)、Velociraptor、Cloudflared、VS Codeトンネルなどの新規サービス登録や設定ファイル改変。
- 認証情報のリセット: WHD内に保存/参照され得るサービスアカウントや管理者アカウントの資格情報は侵害後に再利用され得るため、計画的に更新する。
結論として、CVE-2025-40551のようなデシリアライゼーションRCEは、単発のRCEで終わらず、RMM・DFIRツール・トンネルを組み合わせた“運用型侵害”へ遷移しやすい。再発し続ける脆弱性クラスであるからこそ、パッチ適用に加え、公開範囲の最小化と「プロセス起点の検知」を常設することが、再侵入を抑止する最短経路である。
FAQ
CVE-2025-40551はなぜKEV登録が重要なのか?
KEVは“悪用が現実に起きている”ことを示す運用シグナルである。脆弱性の深刻度(CVSS)だけでなく、攻撃者の投資がすでに始まっている前提で、パッチ適用・隔離・侵害調査を優先順位付けできる。
デシリアライゼーション脆弱性はなぜ繰り返し問題になるのか?
入力境界が複雑で到達経路の把握が難しく、依存ライブラリ上のガジェット条件が更新で変動し得るためである。さらに、Javaシリアライズは互換性目的で残存しやすく、攻撃面が温存されやすい。
wrapper.exe→java.exe→cmd.exeは何を意味するのか?
WHDのサービス実体(Java)が、脆弱性の悪用によりOSコマンド実行へ接続されたことを示唆する。以後のRMM導入やトンネル構築は、その“RCEで得た実行権”の上に積み上がる。
正規ツール(RMM/Velociraptor/Cloudflared)が入っているだけで侵害と断定できるか?
断定はできないが、導入経路(外部URLからのMSIサイレント導入、WHDプロセスツリー起点、短時間での複数ツール展開、設定改変)と組み合わせると侵害の確度が上がる。特にWHDホストへ新規常駐サービスが追加されている場合は高リスクである。
最優先でやるべき対処は何か?
WHDを最新版(ベンダが提示する修正版)へ更新し、管理インターフェースをインターネットから切り離すことである。並行して、侵害調査(プロセスツリー、MSI導入、外向き通信、常駐サービス)を実施し、必要ならホストの再構築と資格情報の更新を行う。
参考文献
- CVE-2025-40551 (NVD CVE API 2.0) — NIST NVD, 2026-01-28
- Known Exploited Vulnerabilities Catalog (JSON) — CISA, 2026-02-03
- SolarWinds Trust Center Security Advisories | CVE-2025-40551 — SolarWinds, 2026-02-06
- Active Exploitation of SolarWinds Web Help Desk (CVE-2025-26399) — Huntress, 2026-02-08
- Active exploitation of SolarWinds Web Help Desk — Microsoft Security Blog, 2026-02-06